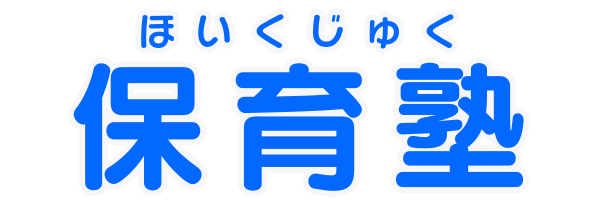保育理念、保育方針、保育目標・・・これらの言葉は、普通に保育をしていたら、深く考える場面はなかったかもしれません。でも、今年度(平成30年度)は今までと違うはずです。「カリキュラム・マネジメント」という言葉が出てきましたよね。「カリキュラム・マネジメント」どころか、見直すはずの教育課程(幼稚園)、全体的な計画(保育所)、教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画(こども園)が、あやふやなところもありますよね。
特に「?」が浮かぶのが、「保育理念」「保育方針」「保育目標」などの言葉ではないでしょうか。「基本理念」「保育ビジョン」「めざす子ども像」「コンセプト」など、区別がついていますか?
この記事では、「保育理念」や「保育目標」などの難しい言葉を、中学生でも分かるくらいに、簡単な言葉で説明しています。「?」が浮かんだままカリキュラム・マネジメントをしようとしていた人は、一旦立ち止まって、意味を考えてくださいね。
「保育理念」「保育方針」「保育目標」などの言葉は難しい
「保育理念」「保育方針」「保育目標」などの言葉は難しいんです。だから、これまで「全然区別がつかない」「よく分からないからスルーしてた」という人も、気にする必要はありませんよ。 この記事を読んだら分かりますから。
「保育理念」「保育方針」「保育目標」「基本理念」「保育ビジョン」「めざす子ども像」「コンセプト」などは、「大事にしてることなんだな」と思うことができていれば十分です。
これまで、なぜ分かりにくかったかというと・・・
ちょっと間違えて表現してある場合がとても多いからです。
ちょっと間違えて表現してあるものを、どれだけ読み込んで考えても、間違った使い方を覚えてしまうことになります。だから、これまで「よく分からないから・・・ようするに大事なことでしょ。」くらいにスルーしてきた人のほうが、むしろ正解です。
「そんな大事なこと、間違えて使ってあるはずないでしょ」と思いますよね。でも、間違えて使ってある場合がたくさんあるんです。大手の会社がやっている保育所なども、けっこう間違えています。何も気にせずに書き方を参考にすると、おかしなことになりますよ。
「保育理念」「保育方針」「保育目標」などの意味を、一言で表すと
保育理念
保育理念とは、「『うちの園の保育とはこうあるべきだ』という、最も根本的な考え方、理想」です。
「基本理念」も「保育理念」と同じように使われます。「保育」ではなくて「基本」なので、保育以外のことも含むことができます。たとえば、保幼小中一貫であれば、「保育理念」とも「教育理念」とも言えませんよね。そういうときは「基本理念」という言葉を使います。市区町村が行う事業なども「基本理念」という言葉が使ってあります。会社だと「経営理念」という言葉があります。
コンセプトという言葉もあります。コンセプトとは、「あるものの特質を、短く分かりやすい言葉で示したもの」です。「保育理念」や「経営理念」は、一般の人、初めての人には難しいので、コンセプトで分かりやすく表してあることがあります。
保育方針
保育方針というのは、「保育をするときのおよその方向」です。
「理念」は抽象的だったり理想が高すぎたりします。「理念」で表したことに近づくために、「どの方向に進めば良いか」ということを具体的に表してあるのが「方針」です。
保育目標
保育目標というのは、「保育をする上で目印となるもの」です。
書き方の参考にするべきなのは、幼稚園教育要領解説や、保育所保育指針解説、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説です。幼稚園や保育所の目標は、「~を養う」「~を育てる」「~を培う」というように書いてあります。
保育ビジョン
保育ビジョンというのは、「実現に当たって、理念を具体化したもの」です。
「経営ビジョン」はよく聞きますが、「保育ビジョン」が示してあるのを見たことはほとんどありません。
めざす子ども像
めざす子ども像というのは、「こんな子どもになってほしいなという理想の姿」です。
他の言葉と違い、めざす子ども像だけ「~な子ども」「~する子ども」のように表します。
「保育理念」「保育目標」のなどの関係を図で表すと

保育理念は、理想なので頂上です。あくまでも理想なので、すぐに達成されるものではありません(理念を分かりやすく簡単に表したものがコンセプトです)。
保育ビジョンは、理念を具体化したものなので、理念の下にあります。
めざす子ども像は、多くの保育所、幼稚園で、ビジョンと同じように使われています。理念を具体化し、子どもの姿で表したものです。
保育目標は、理念やビジョンまでの途中にある目印です。
保育方針は、理念やビジョンへの方向を示すものです。
「保育理念」「保育目標」などを表す上での問題
「保育理念」や「保育目標」などは、どのように使うかが難しいです。理念が1番の基になって、それからビジョンの代わりに子ども像があって・・・というのは分かりましたね。
でも、自分の園の「保育理念」「保育目標」「保育方針」は、正直なところ区別がつかない・・・ということはありませんか?
一般的には、目標というのは数値で表すことが多いです。「今期は10%コストの削減をめざす」「3ヶ月以内に売り上げ4%増」みたいな感じです。
保育の現場では、数字をほとんど使いませんよね。 幼稚園教育要領解説や、保育所保育指針解説、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説の目標も、そこまで具体的なことではなく、ちょっと規模の大きいことが書いてあります。
そして、園によっては、理念を詳しく表し過ぎていることもあります。ですので、「保育理念」「保育目標」「保育方針」の区別がつかなくなるんです。
- 「理念」をシンプルに表す
- 理念を具体的に表した「ビジョン」を表す
- 「目標」の代わりに「子ども像」で表す
- 「方針」を表す。
という書き方だと、区別がつきやすいかもしれません。
「理念」や「目標」と書いておきながら、子どもの姿で表している園もあります。でも、それは一般的な感覚とは違います。できれば、「園のしおり」など、保護者や市役所の人が見るものは、一般的な人が使うのと同じような言葉の使い方をしたいですね。
とにかく、意味を分かった上で、自分の園に合ったものをつくりましょうね。
この記事に関連している記事はコチラ↓
- 【本当はみんな知っている】幼稚園・保育所のカリキュラム・マネジメントとは
- 幼稚園・保育所の「教育課程・全体的な計画」と「カリキュラム」の違いとは【小中学校とは別物です】
- 教育課程・全体的な計画の「期」とは【ちゃんとした意味を知っていますか?】
- 「保育課程」と「(保育所の)全体的な計画」と「(幼稚園の)全体的な計画」との違い
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。「もっといろいろと知りたい」という方は、ホームページや、このサイトの記事が一覧になったサイトマップを、研修・ワークショップなどについて詳しくは「保育塾」の取り組みをご覧ください。
また、質問・ご要望などはお問い合わせフォームから、ご連絡ください。

管理人うち(@uchi70794834|Twitter)
Follow @uchi70794834
保育塾代表
2人の娘の父親
公立幼稚園・幼保園・大学の附属幼稚園で勤務の後、保育塾を立ち上げる。
ラッパ吹き。小学生を中心に、20年以上いろんなバンドを指導しています。
保育士・幼稚園教諭のみなさんが、ほんの少しだけ余裕をもって仕事ができたら、プラスの循環が生まれます。
ほんの少しだけ余裕をもって仕事ができたら、ほんの少しだけ子どもが落ち着いて、そうするとまた、ほんの少しだけ余裕ができて、効率良く仕事ができる方法を調べたりして・・・
そんなプラスの循環の始めの一歩、小さな余裕を生み出すお手伝いをしています。あなたが読んだこの記事が、そんな始めの一歩になったら嬉しいです。